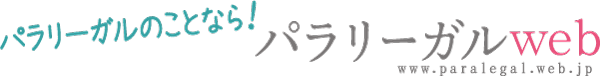
■お昼休みについて
皆さん初めまして。私は、入所し4ヶ月経つ新人事務員です。
私の事務所は先生1事務員1体制で、
入所時から先輩事務員もいなく、法律も知らない状況の中で、毎日悪戦苦闘してます。
皆さん質問ですが、お昼休みはどうしてますか?
私は、なかなかお昼を1時間まともに摂った事がないのです。
先生にいうと、法律事務所は会社と違うから、とれない事務所が多いといわれました。
せいぜい摂れて、25分です。最近は、体調を崩しがちで困っています。
みなさんも、そんな感じでしょうか?
もう1つ、先月から多忙で、先生が急に2月に入りミスノートを作成して下さいと言われました。
私の中で、先生が言っている事が理解出来なく、ミスというよりも、先生の伝達不足が多いような感じがしますが。
先生は、70歳位で手もふるえており、字もなかなかまともに読み取れません。
ミスノートについて、皆さんはどう思われますか?
私は、解雇されるのか?と不安です。
2/4 17:37 うちはお昼休憩中は留守番電話を設定して、12時から1時は...
うちはお昼休憩中は留守番電話を設定して、12時から1時は対外的な電話応対をお休みします(ただ、緊急の案件で、書面を作成したり、急いで外出したりという例外はありますし、自分の判断で、電話をとらなくてよい昼の間に集中して処理したい案件を処理することはあります)。
知り合いの事務所の事務員さんは、本当はお弁当持参がいいのだけれど、昼に事務所に居ると、結局電話応対をしなければいけないから、休憩にならないので、毎日外食している人もいます。
1対1の事務所は弁護士が王様でありルールブックだというような状況になりがちなので、弁護士なのに労働基準法がなんたるかを理解しない弁護士の元では非常に働きづらいと思います。
ミスノートなるものは初めて聞きました。
自分で手控えとして、一回やった間違いをしないように記載するというのであれば分かりますが、ミスを記録しろって・・。
だったら先生の指示も分かりやすくすべて書面にして下さいってところでしょうか(あるいは指示内容を全部書き取ってこれでいいですかと見せて確認でしょうか)。
いずれにしても弁護士の人格に疑問を感じたら辞めるというのはひとつの方法だと思います。
2/5 9:44 昼休みは、確かにアバウトですね。うちも人が少ないため外食...
昼休みは、確かにアバウトですね。うちも人が少ないため外食はできません(してもいいのでしょうけど遠慮しています)。
また、電話がかかってきたら、食事中でもお茶で飲み下して電話に出ます。そうなると、1時間きっちり休みを取れていることはないと思いますが、とりあえず1時まではネットサーフィンしたり(先生が許容してくれているので)、読書をしたり、13時までは休憩中オーラを全開にしています。
なお、うちは弁2事務2ですが、事務員が用事で出払ってしまうことも稀にあります。事務員がいないときは先生が電話に出てくれたり、留守電にまかせたりしているようです。
ミスノートってなんですか?自分のミスを書いて先生に出すんですか?? 嫌味なジジイですねー。そんな人にはデスノートで十分ですよ。ははは。
ただし、「先生が言っている事が理解出来なく」とおっしゃっている部分は多少気になります。しつこいと思われても、「~~ということですか?」と念押ししたり確認する努力は、やはり必要ではないでしょうか。そこは食い下がってはいけない所だと思いますので。
頑張ってくださいね!
2/5 12:57 労基法違反じゃな。法律事務所は会社とちがうとは・・・。 (...
労基法違反じゃな。法律事務所は会社とちがうとは・・・。
(休憩)
第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2)
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3)
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
我が輩は、違う事務所への転職をおすすめします。