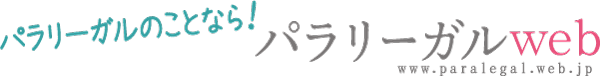
■認定試験ボーダーライン
本日試験受けて来ました。
弁護士会会場では、後半六法をめくる音がこだましていました。
以外に難しかったような気がするのは、自業自得でしょうか?
皆さん、この試験のボーダーラインはどうなんでしょうか?(涙)
みなさんの感想をお聞きしたいです。
7/27 19:05 メッケさんのおっしゃるとおり、この試験及び研修はあいまい...
メッケさんのおっしゃるとおり、この試験及び研修はあいまいな知識を確実にするという趣旨、勉強する中で案外わかっているつもりでもこうして設問で登場すると??となってしまう・・・そういう意味ではよかったと思います。ただ、実務レベルで事務所によって差があるので、実務でやっていないとなかなか入っていかない内容もありました。
合格ラインは、やはり7割ではないかなと思います。出来具合によってはラインを下げることはあっても、上げることはあるんでしょうかね?
7/27 21:07 大阪弁護士会の研修で受験資格を得た者です。 大阪弁護士会の...
大阪弁護士会の研修で受験資格を得た者です。
大阪弁護士会の研修は日弁連の研修と比べて、レジュメ(テキスト)の質が低すぎます。そこで、受験者を受験資格獲得講座ごとにわけて、それぞれ平均点を算出し、仮に平均点に有意の差が認められる場合は得点修正等の相当な措置をとって頂くよう希望します。
この試験の結果が人事評価の重要な資料となる事務所も少なくないと思われますし、転職のための大きな武器ともなりうるものですので、試験の公平性、信頼性を高めるため、科学的、数学的に必要な措置を採るべきです。
また、来年以降はせめてテキストだけでも大阪弁護士会は日弁連と同じものを使用し、このような問題が生じないようにしてください。
7/27 21:25 どうやら9割正解できました。 ところで、第42問の正解は4で...
どうやら9割正解できました。
ところで、第42問の正解は4ではないでしょうか。
7/27 22:15 みなさん、お疲れ様でした。 第42問は、 Fは非相続人Cの...
みなさん、お疲れ様でした。
第42問は、
Fは非相続人Cの半血兄弟にあたるため、全血兄弟であるDの代襲相続人のHに対し、相続分が半分になるため、Hの相続分は3分の2、Fの相続分は3分の1となるため、2番で正しいのではないでしょうか?
4番は、非相続人の兄弟については再代襲は発生しないため、Hが欠格になってもKは相続人にならないと思います。
ところで、
第16問は3番が正しいのではないでしょうか?
2番は少額訴訟判決に基づく強制執行には執行文が不要のため、誤りだと思うのですが…。
7/27 22:23 皆様、お疲れ様です。 試験当日、緊張してしまい、簡単な問...
皆様、お疲れ様です。
試験当日、緊張してしまい、簡単な問題を間違ってしまうなどして7割をきってしまっているようです(涙)
ところで、40問目ですが、イソ弁に聞いてみたところ、死亡日がわかっているのだから、④ではないか・・・と言っておりますが、どうなのでしょうか・・・
すみません・・・
わかる方教えてください。
9月の発表までドキドキですが、あきらめも肝心ですね。
7/27 22:25 第16問ってどんな問題でしたっけ。問題を事務所に置いてき...
第16問ってどんな問題でしたっけ。問題を事務所に置いてきましたので・・・。気になります。
7/27 22:37 マコPさん、おっしゃるとおり、42問は2ですね。
マコPさん、おっしゃるとおり、42問は2ですね。
7/27 23:07 >天神祭りさん >そこで、受験者を受験資格獲得講座ごと...
>天神祭りさん
>そこで、受験者を受験資格獲得講座ごとにわけて、それぞれ平均点を算出し、仮に平均点に有意の差が認められる場合は得点修正等の相当な措置をとって頂くよう希望します。
そういうことをしないで絶対評価を出すために、全国統一の試験をしたのではないですか?
受験資格によって差が生じる可能性は予測できなかったことではないですし、それが心配なら日弁連の研修を受ければよかったのではないでしょうか?
7/27 23:43 ゆいさんへ >そういうことをしないで絶対評価を出すために...
ゆいさんへ
>そういうことをしないで絶対評価を出すために、全国統一の試験をしたのではないですか?
すみませんが、趣旨がよくわかりません。全国統一の試験を実施することとその点数に公平性を保つための修正を施すこととは完全に両立します。
獲得点数のみで評価をするためには、通常前提条件を統一します。
この場合、全国統一の試験をする前提として「全国統一の講習または講習教材」を用いるのが通常です。今回、日弁連は大阪弁護士会の講習や教材が日弁連のそれらと同等であると認定し、この統一性を担保しようとしたのですが、果たしてそれが正しい認定であったのかどうかを、各集団の獲得点数の平均値を用いて、事後的科学的に検証する必要性があると考えています。
>受験資格によって差が生じる可能性は予測できなかったことではないですし、それが心配なら日弁連の研修を受ければよかったのではないでしょうか?
上記の通り、各講習の間に差がないと試験主催者が見解を公表したのを受けて大阪弁護士会講習を受講した者に対し、試験主催者がこのような態度をとることは妥当でないと考えています。日弁連の事実調査が甘かったことの責めを個々の受験者が負わされるべきではないと考えます。
なお、私の主観では大阪弁護士会の講習、教材が日弁連のそれらと比較してチャチだったのですが、このような主観を押し付けるのは私の本位ではなく、また何らデータを分析することなく点数を修正しろと言っているのでもありません。データを分析して統計学等の科学に基づいて修正の必要性が確認できた場合は、それに忠実に行動すべきだといいたいだけなのです。ですから、科学的検証の結果、日弁連講習受講者の点数を加点処理する必要性が確認されれば、そのようにしなければならないとも考えています。
このような得点補正の問題はどの試験にも生じるものであり、統計学で対応可能なものです。このような科学を信頼するという試験主催者として一般的な態度を日弁連も採らなくてはならないと主張しているわけです。
7/27 23:44 レジュメの質が低いと思ったのなら、違う勉強方法をとればよ...
レジュメの質が低いと思ったのなら、違う勉強方法をとればよかっただけのこと。
試験の結果の良し悪しを何かのせいにするのはいかがなものでしょうか。
私は日弁連のテキストもあまり読んでいませんが、9割がた得点できました。