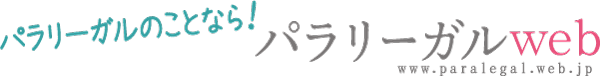
■回答予想です
皆様、大変お疲れさまでした。
昨日の試験後に検討した結果をご参考までに
アップします。
ただ、その場では意見が一致しなかった
2、21、55、56、58は省略します。
(結構多いですね。)
あくまで仲間内での検討ですので、近日中にでる予定の
法律事務職員全国研修センターの回答予想が確実と思いますが。
1.4
3.3
4.1
5.4
6.2
7.1
8.3
9.3
10.1
11.1
12.1
13.2
14.2
15.4
16.2
17.1
18.3
19.4
20.1
22.3
23.1
24.2
25.2
26.1
27.1
28.2
29.2
30.4
31.4
32.3
33.2
34.4
35.4
36.4
37.2
38.4
39.3
40.3
41.2
42.4
43.1
44.1
45.2
46.3
47.1
48.4
49.3
50.1
51.3
52.1
53.2
54.3
57.1
59.3
60.2
7/27 20:57 皆さん、本日もお疲れ様でした。 とても活発に議論されてます...
皆さん、本日もお疲れ様でした。
とても活発に議論されてますね、賑やかで楽しくなってきました。
【問10の選択肢2について】
匿名さん、ご主張は理解できますが、それを考慮しても選択肢2は正しくないと思いますよ。
確かに、本案事件について合意管轄を定めれば、当該管轄で保全申立は可能です。
しかし、それは本案事件レベルで合意管轄を定めた結果、結論としてその管轄で保全申立ができるに過ぎず、決して民事保全レベルで合意管轄を認めたわけではありません。
つまり、本案事件レベルで定められた合意管轄は、民事保全法6条と12条1項により、民事保全レベルで専属管轄と扱われるのです。
それに、問題文にも「民事保全事件においても」という大前提があります。あくまで、民事保全レベルでも合意管轄が認められるのか否か、と解釈するべきです。
【問21について】
選択肢2とされた方が何名かいらっしゃいますね。
結論としては、建物滅失登記の申請には抵当権者の承諾書が必要ですよ。よって、選択肢2は正解肢ではありません。
建物が滅失すると、それを対象にしていた抵当権は、当然に消滅しますね。
しかし、客観的に建物が滅失しても、登記記録上は滅失登記を申請しない限り、存続します。ということは、勝手に滅失登記の申請をされては、抵当権の登記が消えてしまい、抵当権者が登記記録上の不利益を受けてしまいます。
不動産登記法では、登記記録上、自分に有利な登記記録がある場合、それだけで保護に値するという建前になっていますので、たとえ建物が滅失していても、抵当権登記が記録されている事の利益を保護するため、抵当権者の承諾書が必要なんです。
【問56について】
これは自信ないのですが、選択肢1は、契約の申込だけしかされてませんし、相手に聞こえていないという以外に特に情報はありませんので、与えられた情報以外は考慮しないという受験テクニックを前提とするならば、意思表示の合致はありませんので、答えではないような気がするのですが・・・。
これについては、自信のある方の回答を聞いてみたいです。
7/27 21:00 この長い説明は、私さすらい事務員です。 ログインするの忘れ...
この長い説明は、私さすらい事務員です。
ログインするの忘れてました。
7/27 23:54 皆様、試験、お疲れ様でした。 いろいろと勉強して、六法も...
皆様、試験、お疲れ様でした。
いろいろと勉強して、六法も書き込みと付箋でいっぱいでしたが、まったく役に立たず、試験中は、索引と目次を駆使して、必死で六法を使って解答しました・・・。講義でも、六法を使うにとよく言われていたのですが、試験を受けているときにその言葉の意味を痛感しました。受かっているといいなと思っています。
事務員@京都様、解答予想、ありがとうございます。
早速、答え合わせをさせていただきました。
第21問の解答について疑問に思ったので、ご意見させてください。不動産登記法28条で、「表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる」とあるので、建物の滅失登記は、職権ですることができるのでは?と思ったのですが、いかがでしょうか?皆様、ご意見をお聞かせください。
7/28 0:07 【問21について】 結論としては、建物滅失登記の申請には抵当...
【問21について】
結論としては、建物滅失登記の申請には抵当権者の承諾書が必要ですよ。よって、選択肢2は正解肢ではありません。
法律上は、建物滅失登記については抵当権者の承諾書は
求められていないと思います。
添付書類の多くは不動産登記令で定められていますが、
建物滅失登記の添付書類は何も定められていません。
また、不動産登記法に関する各種文献、書式精義にも
抵当権者の承諾書を必要とする記載がありません。
法律、規則、命令、通達、先例に承諾書を必要とする記載がある
のであれば、教えて頂けませんか。
7/28 0:31 第21問については、今年のテキストの第6編戸籍・登記・供託の...
第21問については、今年のテキストの第6編戸籍・登記・供託の23~24ページを参考にして作られているのではないかと思います。テキストをお持ちでしたら、その部分を読まれたらいいと思いますが、問題が微妙なので、正解については判断しかねます。第10問と一緒ですね・・・。
7/28 0:37 私もますます分からなくなりましたが、 ①さすらい事務員様は...
私もますます分からなくなりましたが、
①さすらい事務員様は、誤っている肢を選ぶ問21について、
何故、条文に規定のある3になるのでしょうか?
私は12:56の問21さんと同じ様な理由で2を選びました。
②「承諾書が必要」について探してみたのですが、該当の条文が見当たりません…
ご存知の方がいらっしゃったらどうかご教示下さい。
それとも登記実務上の運用レベルの問題が出されたのでしょうか?
登記は外注ですので実務について理解が浅くて恐縮ですが、
抵当権を登記するのは、第三者に対抗する為ですよね。
仮に承諾が必要だとして、
例えば不可抗力によって既に無くなってしまった建物についても
滅失の承諾をしないことまでして対抗力を保たせる実益はあるのでしょうか?
仕方がないから承諾する抵当権者もいれば、
何か条件をつけなければ承諾をしない抵当権者もいると思います。
その交渉が整わない場合、滅失登記をすべきでもできずに、
しばらくは登記と実態にズレがあるまま放置され、
終局的には登記官が職権によって滅失登記をして結局承諾の無いまま抵当権は消えるんですよね?
つまり、建物が不可抗力で滅失してしまった場合、
抵当権者が承諾をしてもしなくても
手続きの流れに違いはあれど結局は抵当権が消えてしまう。
どんな場合でも承諾書を必要とするのであれば、
「不動産の現況と登記を極力一致させて国民の取引の安全を図る」的な(すみません、うろ覚えです…)
不動産登記法の趣旨からちょっと外れてしまうことになるんですね…
途中から眠気で何が言いたいのか分からない文章になってしまっていたら申し訳ありません。
とりあえず、条文を探してます。規則か何かでしょうか?
法務局に聞いてしまえば早いでしょうね。。
7/28 2:37 問56 レス、ありがとうございます。 この問題は契約の申し込...
問56
レス、ありがとうございます。
この問題は契約の申し込み=意思表示です。ゆえに意思の合致は必要なく、あくまでも意思表示が有効かどうか?だと思います。
つまり、
選択肢1
=口頭で意思表示をした→意思表示有効。
※相手に聞こえない=表意者の過失であるというだけで口頭でした意思は撤回しない限り、無効にはならない
選択肢2
=意思表示有効・さらに契約成立(契約が無効かどうかは、この問題からは分からないが…)
選択肢3
=郵送で意思表示をした(到達した時点で意思表示の効力が発生) ←この時点で受け取った者が表意者の意思を確認・回答しなくても、意思表示自体有効となる。
選択肢4
=例えば、うなづく行為や手話など言葉を伴わない動作としてあげられます。いずれにせよ、契約を申し込むという意思を表示したならば、意思表示は有効。
よって、選択肢1の何の効力もない。いうのが誤りのような気が致します。
いかがでしょうか?
7/28 2:38 問56 レス、ありがとうございます。 この問題は契約の申し込...
問56
レス、ありがとうございます。
この問題は契約の申し込み=意思表示です。ゆえに意思の合致は必要なく、あくまでも意思表示が有効かどうか?だと思います。
つまり、
選択肢1
=口頭で意思表示をした→意思表示有効。
※相手に聞こえない=表意者の過失であるというだけで口頭でした意思は撤回しない限り、無効にはならない
選択肢2
=意思表示有効・さらに契約成立(契約が無効かどうかは、この問題からは分からないが…)
選択肢3
=郵送で意思表示をした(到達した時点で意思表示の効力が発生) ←この時点で受け取った者が表意者の意思を確認・回答しなくても、意思表示自体有効となる。
選択肢4
=例えば、うなづく行為や手話など言葉を伴わない動作としてあげられます。いずれにせよ、契約を申し込むという意思を表示したならば、意思表示は有効。
よって、選択肢1の何の効力もない。いうのが誤りのような気が致します。
いかがでしょうか?
7/28 9:23 法務局に聞きました。 承諾書は不要。 抵当権者が承諾してい...
法務局に聞きました。
承諾書は不要。
抵当権者が承諾していることの調査報告書があれば良いとのことでした。
因みに、テキストにも、承諾書や取壊し証明書がなくても登記官が現況調査し、取り壊しが確認できれば滅失登記が為される旨の記載があります。
そうであれば、承諾書は不要と思います。
さらに、滅失登記は所有者に申請義務があります。
抵当権者の承諾がないから申請できないとなれば、義務を履行できません。
そんな制度にはなっていないと思います。
いずれにせよ、テキストにも正しい記載がなく、設問の肢としても疑問がありますね。
7/28 12:44 皆さん、こんにちは。 すみません、問21ですが、完全に私...
皆さん、こんにちは。
すみません、問21ですが、完全に私が間違ってました。
先程、登記に詳しい職場仲間に確認したところ、抵当権者の承諾書は不要とのことでした。
承諾書の提出を定めた規定はどこにも無いが、法務局によっては、抵当権者から文句を言われるのを嫌がって、承諾書を要求するところも中にはあるようです。
どこかで承諾書が必要との記載を見た事があったので、選択肢2は答えではないと思ったのですが、全く違ってました。
匿名さん、いろいろ調べて頂き、ありがとうございます。