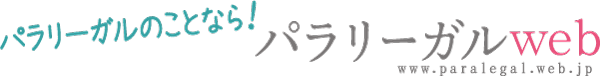
■移送申立て
シンプルに質問をさせていただきます。
提訴後、被告から移送申立てがありました。
裁判所が移送申立てに対する決定をする前に、
被告が答弁書を出してきました。
これって、応訴管轄(という言葉が適切かわかりません)が成立して、
移送申立てを被告自ら無効にしたっていう状況になるんでしょうか?
(提訴した裁判所は普通裁判籍であるのですが、嫌がらせ的移送申立てでした)
もしご存じのかたは、民訴法のどのあたりを読むとわかるのかも教えていただけると
助かります。
よろしくお願いします。
12/10 9:41 そう考えられるかも知れませんので、管轄裁判所に確認が一番...
そう考えられるかも知れませんので、管轄裁判所に確認が一番と思います。
12/10 12:45 弁護士ですが。 移送の申立と答弁書は一緒に出すのが普通です...
弁護士ですが。
移送の申立と答弁書は一緒に出すのが普通です(少なくとも私の中では)。
というのは,第1回目の弁論期日で,移送申立が認めらず,しかも答弁書が出ていないと,欠席判決で敗訴になりかねないからです(まあ普通は,結審しても弁論の再開を申し立てるでしょうけれど)。
で,答弁書が出ていても,まず移送の話からしますので,応訴管轄という扱いにはなりません。
民訴の規定ということですが,ここはあまり自信はないのですが,移送の判断があるまでは,答弁書の陳述が留保されているのではないかと思います。
答弁書や準備書面は,弁論期日などで「陳述します」と言って,初めて答弁等をしたことになりますので。
12/10 21:52 第一回口頭弁論期日の前なら移送の申立をしても,通常答弁書...
第一回口頭弁論期日の前なら移送の申立をしても,通常答弁書は予備的措置として出してくるのかと思います。
応訴管轄(民訴12条)はあくまで期日における弁論により応訴となるので,同時に受け付けられた場合でも移送申立書の審査→却下or移送→(抗告があると複雑ですが)→期日で陳述となってはじめて応訴が生じると考えられます。
東京簡裁で相手が移送の申立をした時は,期日を開く→陳述→そのまま移送却下ということがあったのです。が,その場合でも,相手は答弁書は出さざるを得ないので,移送の申立理由が管轄違いによるものではなくても,申立をしている場合は管轄違いの抗弁を提出しているのと同様にみなされるということなのかもしれませんね。
12/15 13:48 とぴ主です。 答弁書は、移送申立と対立するものではないんで...
とぴ主です。
答弁書は、移送申立と対立するものではないんですね。
ありがとうございまいした。勉強になりました。